2025年7月1日、佐嘉神社記念館で開催された、株式会社オープン・エー (Open A)代表取締役・建築家の馬場正尊氏による佐賀市まちづくり講演会「松原公園からはじまるパークナイズ/公園化する都市~今よりちょっとハッピーな未来をつくるために~」に参加しました。
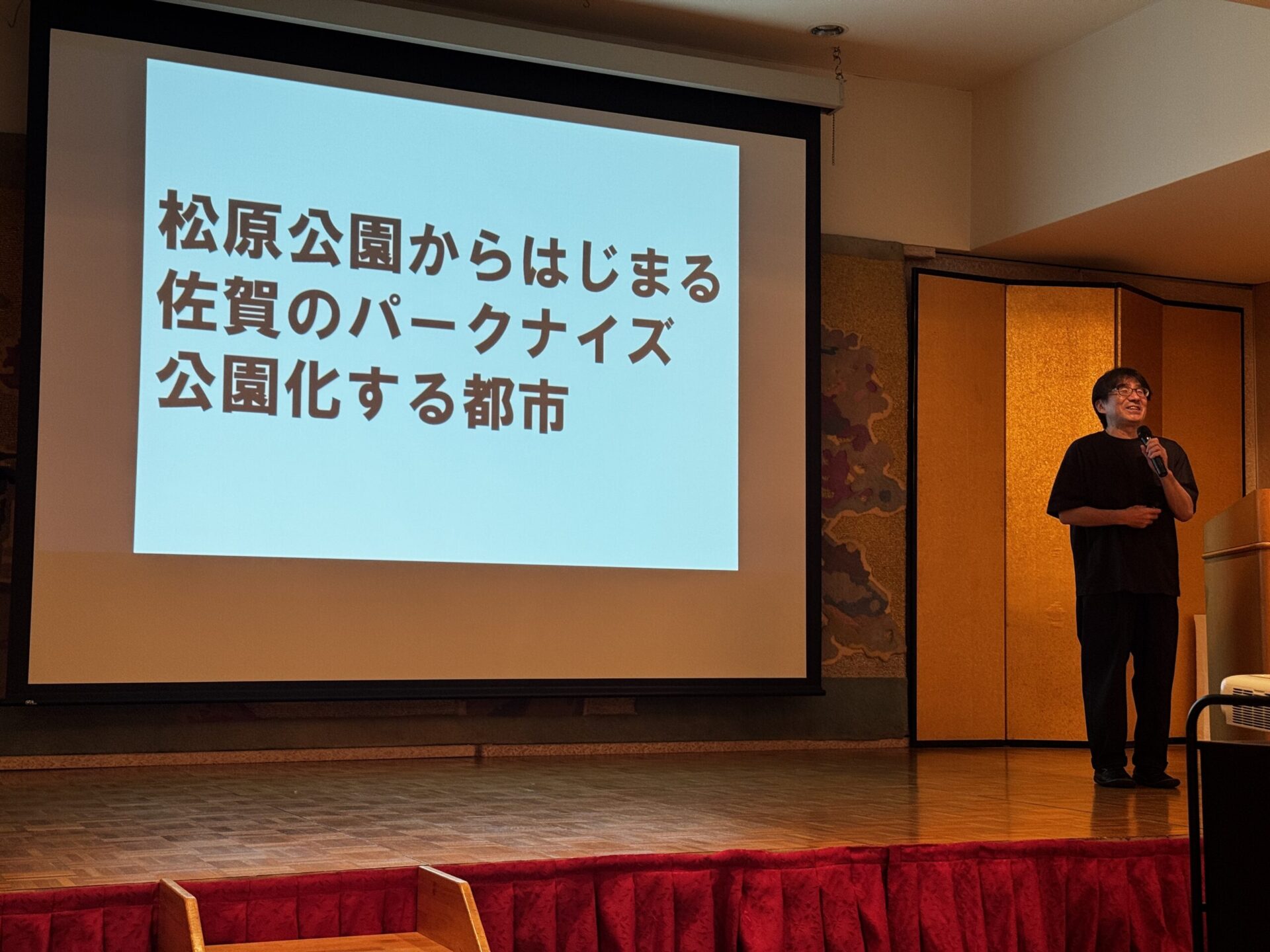
講師の馬場氏とは、今から10数年前、私が環境学生団体「チャリさがさいせい」で自転車活用のまちづくり活動に取り組んでいた頃にお会いして以来となります。当時から、リノベーションという手法で都市に新しい価値を生み出してきた馬場氏の視点に刺激を受けたことを覚えており、期待を胸に会場へ向かいました。
「パークナイズ」という未来のつくりかた
「パークナイズ(PARKnize)」――それは「Park(公園)」を動詞形にした、馬場氏による造語。講演は「公園化する都市」という、聞くだけで期待が膨らむコンセプトから始まりました。人口減少社会において、空き地や空き家を単なる「コスト」として捉えるのではなく、芝生や緑、人々の居場所といった「公園」のような価値ある空間へと転換していく。この視点の転換は、ともすればネガティブに語られがちな地方都市の未来に、明るい光を灯すものだと感じました。
私が佐賀市市民活動プラザで働く者として特に印象に残ったのは、市民参加を促す際の「問いかけ」の違いです。馬場氏は、ワークショップなどで「何がほしいですか?」と問うのではなく、「この場所で、あなたは何をしたいですか?」と問いかけることの重要性を強調されていました。
「ほしい」という問いは、どうしても行政に対する「要求」になりがちです。しかし、「何をしたいですか?」と問われると、私たちは途端に「自分だったらどう使うか」という当事者意識を持つきっかけになります。このアプローチは、まさに「場をつかう人」を育む本質であり、ハッとさせられました。
私自身がセミナー会場に使わせていただいたことがある江北町「みんなの公園」も紹介されました。そこでは、その問いかけから「マルシェをやりたい」「青空教室を開きたい」といった市民の能動的なアイデアが生まれ、公園が真に「みんなの」場所として育っていくプロセスが語られました。ハード(設備・デザイン)を整えるだけでなく、ソフト(運営・マネジメント)を、それも市民を巻き込みながら設計していく。その両輪があって初めて、公共空間は持続的に輝きを放つのだと改めて学びました。
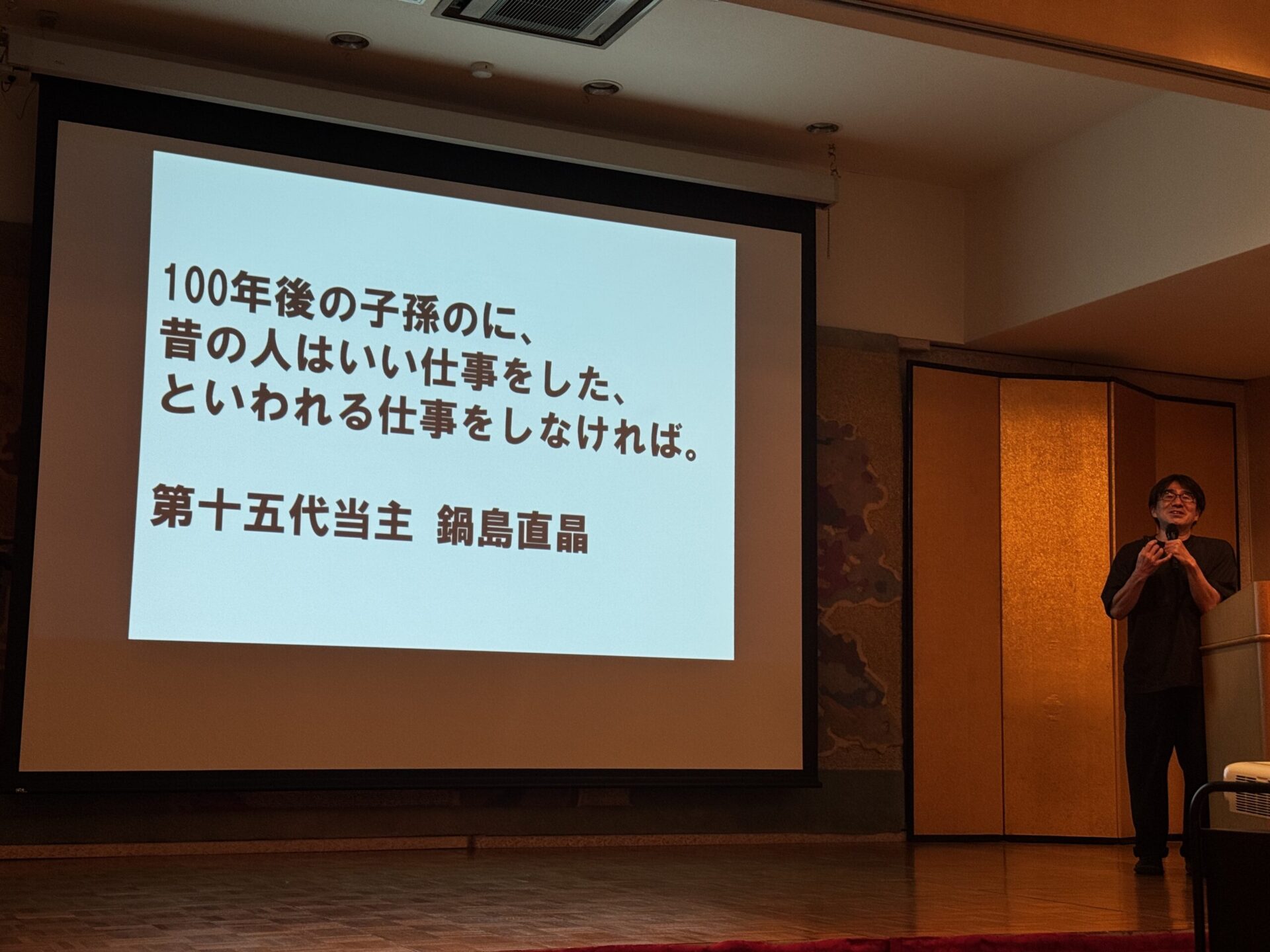
当事者を「育む」という、私の仕事
講演を拝聴し、私は自らの役割を再認識させられました。普段、中間支援組織として市民活動やまちづくりを支援する中で、どこかで「良い景観」、「良い施設」といったハード面を整えることに関心が向きがちだったかもしれません。しかし、馬場氏のお話は、都市の景観はもちろんのこと、何よりもその場所をつかう人、その場を育てる人、すなわち「当事者を育む」ことこそが、私にとって最も重要な役割であると教えてくれました。
完璧な計画を待つのではなく、小さな「手がかり」や「余白」を用意し、市民が「これなら自分もできるかも」と創造性を発揮できる機会を創出していく。そして、生まれた小さな「やりたい」という想いを繋ぎ、実現に向けて伴走する。これこそが、中間支援組織に求められる役割そのもの。
私も「当事者を育む」という視点から、市民と行政、専門家をつなぐハブとなり、様々なプロジェクトに積極的に関わっていきたいです。市民一人ひとりが「ここは私たちの場所だ」と心から思えるような、そんな未来の風景を、皆さんと共につくり上げていきたいと強く感じた、実り多き講演会でした。

